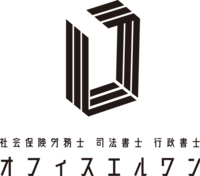就業規則の作成変更・助成金の申請代行なら、社労士オフィスエルワン【東京 千葉 船橋】にお任せください。
退職金制度

退職金支給は会社の義務ではありません。しかし、退職金を支給する会社は就業規則で退職金に関する定めをしておく必要があります。
退職金制度導入のために
トラブル回避のポイント
●対象労働者の範囲、退職金の決定・計算・支払い方法、退職金の支払い時期に関する事項を就業規則に定めておく必要があります。
●退職金には、功労報奨、賃金後払い、老後の生活保障等の意義があります。自社における退職金支給の目的を考えましょう。
退職金制度について就業規則に定める
退職金を支給するかどうかは会社が自由に定めることができますが、対象労働者の範囲、退職金の決定・計算・支払い方法、退職金の支払い時期に関する事項を就業規則で定めたら、そのルールに従って支給しなくてはなりません。会社の都合で個別に不支給・減額をすることはできません。また、すでに定めのあるルールの変更についても注意が必要です。
退職金の支払い対象者の範囲、支給額について
対象労働者について明確にしておく必要があります。正社員のみを対象とする(パートタイマーや契約社員等の非正規社員を対象外にする)場合は、あいまいな表現(「従業員」に支給する、など)になっているとトラブルの原因になるので必ず確認しておきましょう。
支給額は勤続年数、在職中の業績、退職理由(自己都合、定年退職)で異なる金額を定めるのが一般的です。
退職金の支払い時期について
あらかじめ就業規則で定めた時期が退職金の支払い時期になります。必ず支払期日を定めておきましょう。退職者から早く退職金を支払ってほしいとの請求があっても、就業規則で退職金の支払い時期を退職の日から2か月以内と定めている場合、会社はその時期(期限)までに支払えばよいということになります。
退職金制度の目的
まずは自社における退職金支給の目的を検討するところから始めましょう。一般的な退職金を支給する目的としては、①在籍期間の貢献度における功労報奨、②在籍期間の賃金の後払い、③老後の生活、などがあげられます。これを踏まえて、自社における退職金制度の目的をしっかり考えることで、退職金を支給しないことも含め、退職金に関する自社の方向性がきまります。
規定例
第●条 退職金の適用範囲
退職金制度は、本規則第●条(従業員の定義)●項に定める正社員にのみ適用する。同条●項~●項に定める従業員(正社員以外の契約社員、パートタイマー等)には適用しない。
第●条 退職金の支給対象者
退職金は、勤続年数満●年以上の正社員が以下のいずれかに該当して退職する場合、その者(死亡による退職の場合はその遺族)に支給する。
①定年による退職
②死亡による退職
③会社都合による退職
④休職期間満了による退職
⑤自己都合による退職
第●条 退職金の支払時期
退職金は、原則として退職の日から〇カ月以内に支給対象者に対して通貨で直接支払う。ただじ支給対象者が希望する場合、指定する銀行口座への振り込みにより支払うものとする。
お問合せはこちら

お気軽にお問合せください
お問合せ・ご相談はお電話・お問合せフォーム・メールにて受け付けております。まずはお気軽にご連絡ください。
Email:info@syarousitm.jp
電話受付時間:10:00〜11:45、13:00〜16:30
(土日祝を除く)
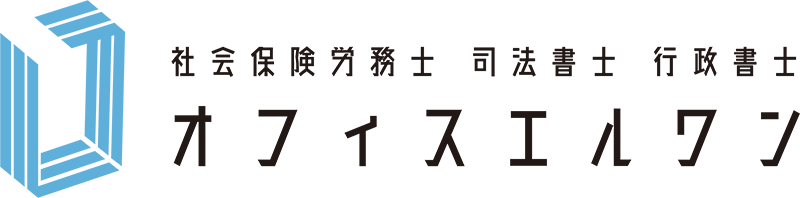
法的サービスを1つに