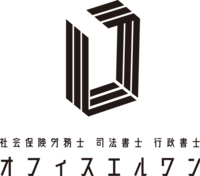就業規則の作成変更・助成金の申請代行なら、社労士オフィスエルワン【東京 千葉 船橋】にお任せください。
訪問介護事業の開業準備

ここでは、訪問介護事業を開業するために準備しなければならないことを考えていきます。代表的なことは以下のような事柄です。
1 法人の設立
2 損害賠償保険の加入
3 ヘルパーさん等の従業員の雇用
4 事業所の賃貸借契約
5 備品の購入
訪問介護の開業準備で行うべきこと
法人の設立
訪問介護事業をはじめるためには、法人格が必要です。この場合に、法人の種類は問われませんので、株式会社でも合同会社でもNPO法人でもかまいません。とにかく法人を設立する必要があります。
さて、法人の設立にはある程度の期間が必要です。法人の種類によって設立までの時間は異なりますが、おおむね次のとおりです。
法人の種類 設立までの期間
株式会社約3週間
合同会社約2週間
NPO法人3ヶ月~5ヶ月
一般社団法人約1ヶ月
法人の設立が完了していなければ、訪問介護事業の指定申請ができませんので、開業開始日から逆算して考える必要があります。介護事業をはじめようと考えたら、まず法人の設立にとりかかることが必要です。
法人設立の注意点
法人を設立する場合には注意していただきたいことは次のような点です。
1 事業の目的
法人を設立する場合には、その法人が事業として何を行うのかを定款などに記載して、登記する必要があります。訪問介護事業の場合には、「介護保険法に基づく居宅サービス事業」のように記載します。
また、事業目的は、これから行う予定の事業も記載することができます。例えば、開業当初には訪問介護のみを行うが、将来的にはケアマネもやる予定というような場合には、「介護保険法に基づく居宅介護支援事業」のように、ケアマネに関する事業目的も記載しておくこともできます。
事業目的については、各自治体によって、このように記載してほしいという内容が公開されている場合もありますので、設立手続きを行う前に確認しておくことが必要です。
2 役員の人選等について
助成金を検討している場合には、役員、出資者、資本金について、検討することが必要です。例えば、日本政策金融公庫の新創業融資制度は融資の要件として「自己資金の要件」があり、資本金額の3分の1以上の自己資金が確認できなければなりません。資本金額が300万円とすれば、100万円以上は、銀行からの借入金などではなく、自己資金(自分の財布)から出資している必要があります。
損害賠償保険加入の注意点
損害賠償保険に加入する際に注意しなければならないことを述べます。
注意点① 損害賠償保険に加入していることを証明する書面
加入を証明する書面としては以下のようなものがあります。
■ 付保証明書
■ 保険証券
付保証明書とは、その名のとおり保険に付していることを証明する書面です。保険契約を行って、保険料を支払うと発行してもらえます。
保険証券は、保険の加入証明書ですが、どこの保険会社でも証券の作成には、一定の期間を要します。つまり保険料を支払ってもすぐには発行されないことが多いと思います。これに対して付保証明書は保険料を支払えば、すぐに発行してもらえます。
ですから、指定申請までに時間がないようなケースでは、付保証明書を発行してもらうほうが良いと思います。
注意点② 保健期間
保険期間とは保険が適用になる期間です。通常は「平成○○年○月○日午後4時から平成○○年○月○日午後4時まで」というように保険証券などに記載されています。保険の開始期間は通常「午後4時」となっています。
しかし、事業開始が平成25年9月1日の場合に、保険期間が「平成25年9月1日午後4時から平成26年9月1日午後4時まで」となっていると、平成25年9月1日の午前10時に発生した損害には、保険が適用されないこととなります。
介護事業指定申請の際には、この点を役所から指摘されますので、保険を申込みする際には、保険期間を、平成25年9月1日の午前0時からとするように保険会社に依頼しておく必要があります。
注意点③ 保険は早めに申し込む
保険の加入はすぐにはできません。2週間程度はかかるでしょう。保険の加入は、指定申請を行うまでに完了しておく必要がありますので、事業所の所在地を決定したらすぐに加入の手続きをとりましょう。
ヘルパーさん等の従業員の雇用
訪問介護事業には、管理者、サービス提供責任者、訪問介護員(介護ヘルパー)が必要になります。それぞれの人員基準はこちらの記事(訪問介護の人員基準)を確認してください。特にサービス提供責任者や訪問介護員は、従業員として採用することが必要になってくると思います。
訪問介護事業の開業申請(指定申請)を行う際に、従業員の勤務状況や訪問介護員の資格を証明する資料、雇用契約書などを提出することになりますので、人員の確保は、開業前に行う必要があります。
具体的には、従業員の募集を行い、雇用契約を結んでおく必要があります。従業員が実際に勤務するのは介護事業の指定を受けてからとなります。
従業員の募集は、様々な方法が考えられます。次のような方法です。
■ 職業安定所(ハローワーク)に求人を出す
■ 求人誌に従業員募集の広告を出す
■ 知人に紹介してもらう
■ 事業所のホームページに掲載する
■ 人材派遣会社から派遣してもらう
職業安定所や求人誌に募集をかければ、幅広い人材を集めることが可能です。しかし、介護ヘルパーという職業は人物本位なので、信頼のできる人材が必要であることをよく見極める必要があります。
その点、知人からの紹介の場合には、紹介する側も紹介する人物を知っているケースが多いと思いますので、信頼できる人材を確保できる可能性が高いと思います。
また、費用の面から考えると、事務所のホームページをお持ちの場合、そこに掲載するのであれば費用はかかりませんし、職業安定所への求人広告は無料です。
雇用契約については、開業前に働いてもらう予定の人と契約書を取り交わしておくことが必要です。雇用契約書には次のような事項を記載する必要があります。
■ 雇用期間
■ 賃金に関すること(賃金額、支払い方法、支払時期、割増賃金の計算方法など)
■ 労働時間に関すること(所定労働時間、所定労働時間を超える労働の有無など)
■ 勤務する場所
■ 退職に関する事項(解雇の事由、解雇予告手当についてなど)
このような事項を記載した雇用契約書を作成して、使用者と従業員が署名捺印することが必要です。
開業前に雇用契約を結んでおくことが必要ですが、「雇用期間」は訪問介護事業の指定を受けてからでかまいません。実際に営業を開始できるのは指定をうけてからなのですから。
事業所の賃貸借契約
訪問介護事業の事業所には、以下の3つのスペースが必要です。(詳しくは「設備基準」の記事をご確認ください。)
■ 事務室・・・・従業員が事務を行うため
■ 相談室・・・・利用者さんやその親族が介護相談を行うため
■ 手洗い場・・感染症を予防するため
この3つのスペースが確保できる程度の広さが必要です。事業所を借りようとする場合には、このスペースを確保できるかを考えて物件選びをしてください。
広さの規定は特にありません。ただし、事務室と相談室は区分されている必要があります。パーテーションを使って区分することができればよいのですが、あまり狭いと区分することができない事態になってしまいますので、最低でも事務室は6畳、相談室は4畳くらいは必要になります。
また、居住用の賃貸物件を借りて、そこを事業所とすることもできますが、必ず賃貸借契約書には、「事業用(介護事業所)として利用する」旨の記載をしてください。居住用のままでは、指定を受けることはできません。事業用として利用することについて大家さんの承諾を得ることは当然です。
賃貸借契約を行う際に注意していただきたいのは、法人で契約するということです。訪問介護事業を行うのは法人ですから、事業を行う法人で契約することが必要です。
ですから、賃貸借契約を結ぶ前に法人を設立しておくことが必要です。
自宅を事業所とする場合であっても、契約書が必要になります。
どういうことかというと、例えば法人の代表者が所有してる物件を事業所とする場合には、法人が代表者から借りるという形をとります。
つまり、法人と代表者の間で賃貸借契約を結ぶことになります。
賃貸借契約書は、指定申請の際に提出しますので、その時までに契約を済ましておくことが必要です。
備品の購入
訪問介護事業を開業するまでに必要な備品を用意しましょう。ここでいう開業までとは、「指定申請を行うまでに」という意味です。
なぜなら、指定申請を行う時に事業所内部の写真を提出しますが、必要な備品がすべてそろった状態で写真撮る必要があり、指定申請書には事業所の電話番号を記載する必要があるため、電話番号も取得しておく必要があります。
必要な備品は次のようなものです。
- 電話、FAXは開業前に開通しておく
- 事務机従業員の全員が利用できる分は用意しましょう
- 相談室のテーブル3~4名程度が同席できる程度
- 椅子事務室は従業員の分、相談室は3~4名程度の分
- 手洗用せっけん感染症予防のため洗面所に用意しましょう
- アルコール消毒液感染症予防のため洗面所に用意しましょう
- 鍵付きキャビネット利用者さんの書類を管理するためのもの
鍵付きキャビネットは、事務室に配置します。プライバシー保護の観点から、キャビネットの中が見えるもの(扉がガラス状のもの)には目隠しが必要です。
事務机は、ヘルパーさんなどの従業員全員分を用意することが望ましいですが、長机のようなもので全員が利用できる程度の長さがあればそれでも大丈夫です。
お問合せはこちら

お気軽にお問合せください
お問合せ・ご相談はお電話・お問合せフォーム・メールにて受け付けております。まずはお気軽にご連絡ください。
Email:info@syarousitm.jp
電話受付時間:10:00〜11:45、13:00〜16:30
(土日祝を除く)
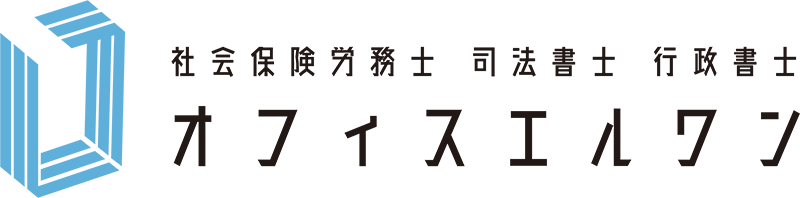
法的サービスを1つに