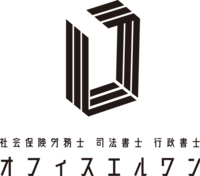就業規則の作成変更・助成金の申請代行なら、社労士オフィスエルワン【東京 千葉 船橋】にお任せください。
労働保険と社会保険の新規適用(加入)手続き
~会社の加入手続き

会社を設立して初めて従業員を採用した時は、以下の手続きが必要です。
会社に関する手続きとして、
- 労働保険の新規適用
- 労働保険の概算保険料の申告
- 社会保険の新規適用
従業員に関する手続きとして、
- 雇用保険の資格取得
- 社会保険の資格取得
- 社会保険の扶養に関する手続き
以下で詳しくみていきます。
労働保険の新規適用手続き~会社の加入手続き
労働保険とは、労働者が業務上の事由または通勤によって負傷した場合などに、その被災労働者や遺族を補償する「労働者災害補償保険(労災保険)」と、労働者が失業した場合に、その労働者の生活や雇用の安定等を図るために必要な給付を行う「雇用保険」を総称したものです。
労災保険・雇用保険ともに、労働者を1人でも雇用する事業は、その業種や規模を問わず、農林水産業の一部を除いてすべて適用事業となります。ただし雇用保険の場合には、1週間の労働時間等の雇用形態によっては被保険者とならないケースもあります。
そのため、その事業主は労働保険料の納付や労災保険法・雇用保険法の定めによる各種の届出義務を負います。
労働保険に加入するための手続き
1 労働者を1人でも使用している事業は、原則としてすべて強制加入
保険関係は、届出時期とは関係なく、その事業が開始された日または適用事業に該当するに至った日に、当然に成立します。
ただし、以下の表の事業は暫定任意適用事業とされ、労働保険に加入するかどうかが、事業主の意思または、その事業に使用されている労働者の意思に任されています。
| 労災保険の暫定任意適用事業 | 雇用保険の暫定任意適用事業 |
| 個人経営の農林水産業で、かつ、次の要件に該当するもの
| 次のいずれにも該当するもの
|
2 一元適用事業と二元適用事業では申告方法が異なる
労災保険と雇用保険とをあわせて1つの保険関係として取り扱い、労働保険料の算定や納付などを労災保険・雇用保険について一元的に処理する事業を「一元適用事業」といいます。
一方で、事業の実態からみて労災保険と雇用保険の適用方法を区別する必要があるため、労災保険と雇用保険の算定・納付を別個(二元的)に処理する事業を「二元適用事業」といいます。この一元適用事業と二元適用事業については次の表をみていただければ理解しやすいと思います。
| 一元適用事業 | 二元適用事業 |
| 右記以外の事業 |
|
労働保険の新規適用手続き(一元適用事業が成立した場合)
労働保険の適用事業となったときは、まず、「保険関係成立届」を保険関係が成立した日から10日以内に管轄の労働基準監督署に提出します。
また、その年度分の労働保険料を概算保険料として申告納付するために、保険関係が成立した日から50日以内に「概算保険料申告書」を管轄の労働基準監督署に提出することも必要です。
労働基準監督署に書類を提出した後に、雇用保険に関する手続きを行います。
保険関係成立届を提出した後、事業所設置の日から10日以内に「適用事業所設置届」を管轄の公共職業安定所に提出します。さらに従業員の雇用保険加入のための手続きを行う必要がありますので、「被保険者資格取得届」を資格取得の事実のあった日(原則として採用の日)の翌月10日までに提出します。
まとめると次の表のようになります。
| 労働基準監督署に提出する書類 | 公共職業安定所に提出する書類 |
|
|
| 添付書類 | 添付書類 |
|
|
労働保険の新規適用手続き(二元適用事業が成立した場合)
二元適用事業の場合には、労災保険にかかる手続きと雇用保険にかかる手続きとを別に行います。
1 労災保険にかかる手続き
「保険関係成立届」を、保険関係が成立した日から10日以内に管轄の労働基準監督署に提出します。加えて、保険関係が成立した日から50日以内(有期事業の場合には20日以内)に「概算保険料申告書」を管轄の労働基準監督署に提出しなければなりません。
2 雇用保険にかかる手続き
「保険関係成立届」を、保険関係が成立した日から10日以内に管轄の公共職業安定所に提出します。加えて、保険関係が成立した日から50日以内に「概算保険料申告書」を管轄の公共職業安定所に提出しなければなりません。
そのほか、一元適用事業と同様に、事業所設置の日の翌日から10日以内に「適用事業所設置届」を、資格取得の事実があった日の翌日から翌月10日までに「被保険者資格取得届」を、それぞれ管轄の公共職業安定所に提出する必要があります。
まとめると次の表のようになります。
| 労働基準監督署に提出する書類 | 公共職業安定所に提出する書類 |
|
|
| 添付書類 | 添付書類 |
|
|
社会保険の新規適用手続き~会社の加入手続き
この場合の社会保険とは、健康保険と厚生年金保険のことを指します。
社会保険においては、下の表に掲げるような会社を設立した際には、事業主や従業員の意思に関係なく健康保険や厚生年金保険に加入しなければなりません。
一方、常時5人未満の従業員を使用して適用業種の事業を営む下の表に掲げる個人事業の事業所は任意適用事業に該当し、必ずしも社会保険に加入する必要はありません。
しかし、非適用業種であっても法人の場合は強制加入となります。
| 社会保険の適用事業・任意適用事業 | ||
| 事 業 | 内 容 | |
| 国又は法人の事業所 | 常時従業員を使用する国・地方公共団体・法人の事業所 | 従業員数に関わりなく強制適用事業所 |
| 個人経営の事業所 | ①製造業、②土木建築業、③鉱業、④電気ガス業、⑤運送業、⑥製造業、⑦物品販売業、⑧金融保険業、⑨保管賃貸業、⑩媒介斡旋業、⑪集金案内広告業、⑫教育研究調査業、⑬医療事業、⑭通信報道業 など | 常時5人以上の従業員を使用する場合は任意適用事業所 |
| 常時5人未満の従業員を使用する場合は任意適用事業所 | ||
| 従業員数に関わりなく任意適用事業所 | |
社会保険に加入するための手続き
事業所を設立し、健康保険・厚生年金保険の適用を受けようとするときは、「健康保険・厚生年金保険新規適用届」を設立した事実の生じた日から5日以内に事業所の所在地を管轄する年金事務所に提出します。
任意で加入できる事業所の場合には、上記の新規適用届とともに「任意適用申請書」を提出し、厚生労働大臣の認可が必要になります。
まとめると次の表のようになります。
| 年金事務所に提出する書類 | |
| 強制加入の場合 | 任意加入の場合 |
|
|
| 添付書類 | 添付書類 |
|
|
また、新規適用の際に、雇用した従業員の資格取得に関する届け出も行う必要がありますので、「健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届」を提出します。
さらに、扶養に入れるべき者がいる場合には、「健康保険被扶養者(異動)届」を提出します。また、満20歳以上満60歳未満の被扶養配偶者がいる場合には、その者を国民年金の第3号被保険者とすることができますので「国民年金第3号被保険者届」も併せて提出します。
| 従業員の入社に関する手続きで提出する書類 | |
|
雇用保険の資格取得手続き~従業員の入社
会社の労働保険の加入手続きと同時に、雇い入れた従業員の雇用保険への加入手続きを行います。
社会保険の資格取得手続き~従業員の入社
会社の社会保険(健康保険・厚生年金保険)の加入手続きと同時に、雇い入れた従業員の社会保険への加入手続きを行います。
お問合せはこちら

お気軽にお問合せください
お問合せ・ご相談はお電話・お問合せフォーム・メールにて受け付けております。まずはお気軽にご連絡ください。
Email:info@syarousitm.jp
電話受付時間:10:00〜11:45、13:00〜16:30
(土日祝を除く)
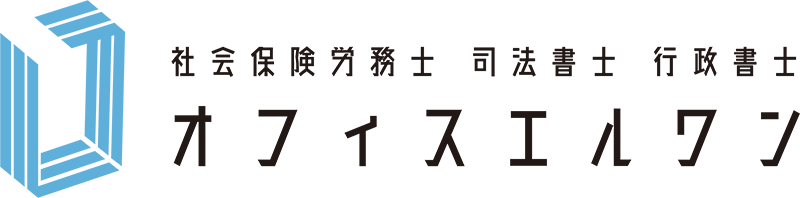
法的サービスを1つに