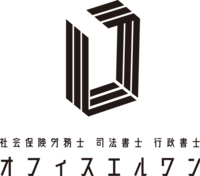就業規則の作成変更・助成金の申請代行なら、社労士オフィスエルワン【東京 千葉 船橋】にお任せください。
年次有給休暇の付与日数

年次有給休暇は論点が多く、確認しておかなければならない事項が多い重点項目です。まずは管理上とても大切な有休発生日を確認することからスタートしましょう。
年次有給休暇の適正な管理のために
トラブル回避のポイント
●年次有給休暇のルールは就業規則に必ず記載しましょう。
●有給の基準日(発生日)の統一を行うと、会社は管理しやすくなり、従業員は法令で定めるタイミングよりも早く有給休暇が取れるメリットがあります。会社のメリット・デメリットと合わせて比較検討しておきましょう
原則的な管理方法の問題点
年次有給休暇の付与方法については、法律で最低限与えなくてはならないタイミングと付与日数が定められています。これよりも遅いタイミングや少ない日数での付与はできません。
ですから、この最低限のルールに合わせて付与するのがひとつの方法です。
しかし、中途採用による従業員が増えてくると、入社日が各人によって異なるケースが増えていきます。
そうなると、全従業員の入社日ごとに細かな管理(誰にいつ付与するのか)を毎月・毎年行わなければなりません。
従業員数が少ないうちはそれほど問題ないかもしれませんが、人数が増えるとこの管理方法はとても煩雑になってしまいます。
一斉に付与する基準日を設ける
原則的な管理方法の煩雑さを解消するのが基準日を設けて一斉に付与する方法です。この場合、法令の定めよりも早いタイミングで付与しなくてはいけません。ここでは4月1に一斉付与するケースで、入社日が異なる2人の例をあげます。
・Aさん:平成24年4月1日入社
・Bさん:平成24年9月1日入社
①1回目(10日分)の付与はここでは原則どおり「入社日から6か月後」
・Aさん平成24年10月1日に10日付与
・Bさん平成25年3月1日に10日付与
②2回目(11日分)の付与は「初回付与後直近の4月1日」
・AさんBさんとも:平成25年4月1日に11日付与
③三回目(12日分)の付与
・AさんBさんとも:平成26年4月1日に12日付与
一斉付与の場合、会社にとっては毎年同じ日に有給付与できるので管理がしやすくなります。従業員にとっては法令より早く有給付与されるメリットがあります。
法定より有休付与日を繰り上げるときの注意点
有休付与日は法定より繰り上げすることはできますが、一度繰り上げした場合は以降その繰り上げた日を基準日にしなくてはなりません。2回目の有休付与日は「初回に付与した基準日から1年後(以内)」です。初回を入社日、2回目を入社日から1年6ヶ月後とはできませんので注意しましょう。
規定例
第●条 年次有給休暇(4月1日一斉付与の例)
年次有給休暇の更新(基準日)は毎年4月1日とし、次の日数を付与する。ただし、入社後6ヶ月を経過しない従業員は更新の対象としない
お問合せはこちら

お気軽にお問合せください
お問合せ・ご相談はお電話・お問合せフォーム・メールにて受け付けております。まずはお気軽にご連絡ください。
Email:info@syarousitm.jp
電話受付時間:10:00〜11:45、13:00〜16:30
(土日祝を除く)
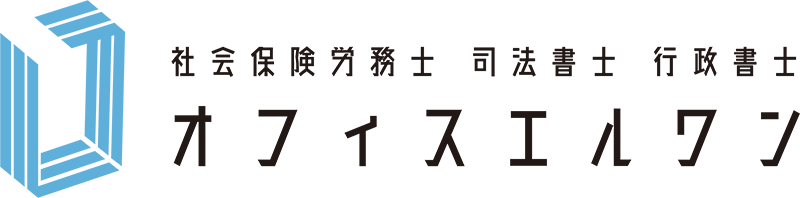
法的サービスを1つに